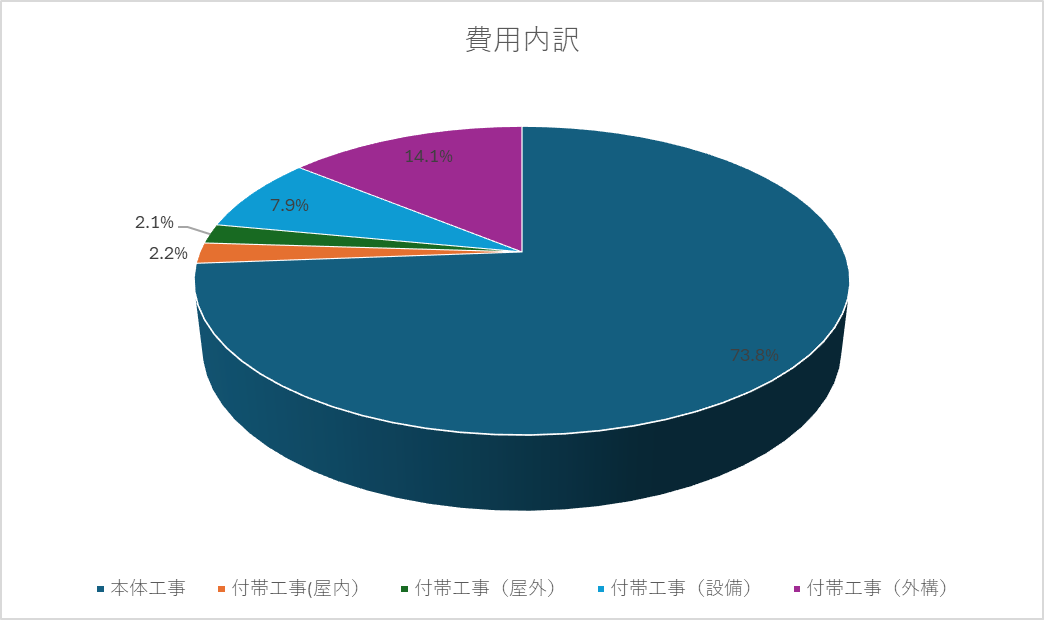浴室点検口問題で、長期優良住宅の認定取得に暗雲が垂れ込めるなか、積水ホームテクノのBATH CORE BCH VI(バスコアBCH6)の導入を再検討することに。
building-dream-home.hatenablog.com
BATH CORE BCH VIとは
積水ハウスと積水ホームテクノが共同開発した、積水ハウス特別仕様の浴室です。 積水ホームテクノのウェブサイトに、積水ハウス様専用サイトが設けられており、仕様を確認することができます。
浴室を清潔に保つために、撥水・発油性の高い人大浴槽や、フチなしの排水口、ステンレス製のヘアーキャッチャー、乾式目地などが採用されています。
DX(デラックス)グレード、SD(スタンダード)グレードの2つのグレードが用意されています。
BATH CORE BCH VIの仕様
DXグレードとSDグレードの違い
DXグレードには、
- カウンタースタイル
- シャワースタイル
- ベンチスタイル
SDグレードには、
- カウンタースタイル
- シャワースタイル
が用意されており、基本的にはあらかじめ設定されたカラーコーディネーション(壁、浴槽、床、天井の色)のなかから選択します。 積水ハウスまたは積水ホームテクノの支店によって対応が変わる可能性もありますが、我が家の担当支店では、カラーコーディネーションの一部変更を認めてくれました(ただし差額発生の可能性あり)。
DXとSD間で基本的な仕様は同じですが、以下のように細かい部分で違いがあります。
- カラーコーディネーションが異なる(SDの天井はホワイトのみ)
- カウンタースタイルのウォールラックグリップに間接照明が付くのはDXのみ(SDではオプション扱い)
- ハンドシャワーは、DXではメタル、SDではホワイト
- 浴室の框やエプロンは、DXでは加飾柄(木目やレザー調)を選択できるが、SDでは単色のみ
カウンタースタイル

ウォールラックグリップという横に長いカウンターと、その上に設置される鏡が印象的なユニットバスです。DXグレードでは、ウォールラックグリップの下に間接照明も付くので、お洒落度アップ。 ウォールラックグリップは、立ち上がったり、浴槽に出入りしたりといった動きをサポートするだけではなく、収納を兼ねていて、シャンプーボトルなどをすっきり収めることができます。
シャワースタイル

シャワースタイル最大の売りは、ハンスグローエ社のオーバーヘッドシャワーを標準装備していること!カウンターがないデザインで、ミニマルな仕様が好みの方にオススメ。
ベンチスタイル(DXのみ)

座ったままの姿勢でシャワーを浴び、身体を洗えるベンチ付き。浴槽へ移動しやすい高さにベンチが設けられているため、高齢者や身体の不自由な方には嬉しい仕様。
その他のオプション仕様
標準仕様の浴槽は、DX・SDともに、リラクゼーション浴槽ですが、節水できるecoたまご浴槽、パールカラーが美しいアクリル人大浴槽も選択可能です。 それ以外にも、
- マイクロバブル
- 自動洗浄機能
- バックマリオンドア
- 浴室換気暖房乾燥機
- 浴室テレビ
- スピーカー
などが用意されています。 このなかでも、バックマリオンドアは、かなりお洒落。色はシルバーのみですが、ステンレス製のバーハンドルが採用されていて、重厚感があります。ガラス面材もカスミとトウメイから選択可能。
長期優良住宅取得を目指す!
長期優良住宅認定を取得できなかった場合、固定資産税の優遇措置が受けられないことで失う金額がかなり大きいことが分かり、浴室点検口を二階に設けることができる積水ホームテクノを採用することに決めました。 我が家の場合、長期優良住宅認定を取るには、マイクロバブルの採用はできないと言われましたが、もともと積極的に付けたかったわけではないので、問題なし。
浴室の壁については、黒っぽい色や、木目調が好みではなく、なるべくテカテカしたパネル感の少ないものということで、「リオージュ」か「ソルティオニックス」かなぁと思いつつ、やっぱり実物を見たいと言うことで、積水ホームテクノに問い合わせ。「ソルティオニックス」については近場のモデルハウスにあることが判明。残念ながら、「リオージュ」はないとのこと。
「ソルティオニックス」をモデルハウスで確認したあと、「リオージュ」については積水ホームテクノのバーチャルショールームで確認でき、最終的に「リオージュ」を選択することに。営業さんがカラーコーディネーションの変更に後ろ向きだったので、あまり我儘を言ってもなぁと弱気になり、DXグレード・シャワースタイルのオーセンティックベージュを選択することにしました。

浴槽の框・エプロンは、「スモーキーウッド」じゃなくて、普通に「ホワイト」でも良いのになぁと思いつつ…。
最終確認中の変更で減額成功!
着工前の最終確認で、浴室の価格を再確認したときのこと。請負契約時はオフローラで入れていた見積り、バスコアBCH6のDXグレードに変更したら、かなりの増額になってしまいました。 我が家の浴室は非常にシンプルで、鏡、タオル掛け、収納棚、風呂蓋フック、物干しバーなど全部外しています。そのため、オプションで付けている浴室換気暖房乾燥機を除くと、SDグレードとの差は、壁と浴槽の色のみ。しかも、浴槽は加飾柄である必要はなく、壁の色を全面「リオージュ」にしたいだけ!なんとか減額できないのかな…と思っていたら、インテリアコーディネーター(IC)さんから「SDグレードにして、カラーコーディネーションだけ変更すれば、減額できるんじゃないですか?」と女神のような一言が。早速見積りを取っていただき、十数万円減額できました。長期優良住宅の認定も無事取れそうで、めでたし、めでたし。