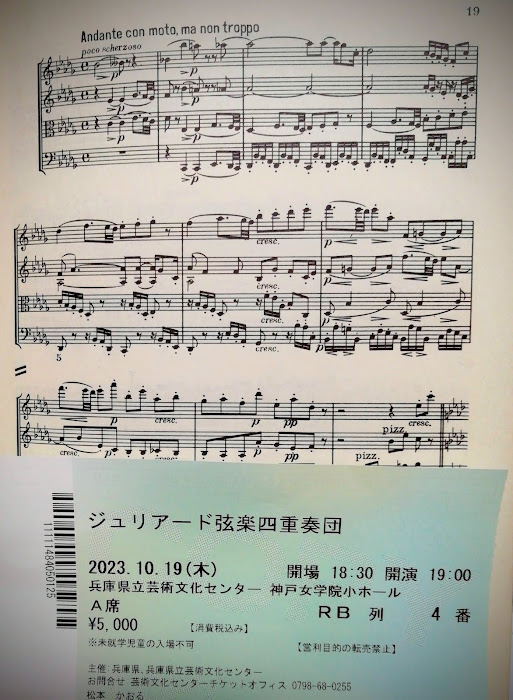心の底から静かに揺さぶられるほんとうにすばらしい物語。これだから韓国ドラマはやめられない。
最終話のお葬式の場面、これほど温かい気持ちになるお葬式は見たことがなかった。
ドンフン役のイ・ソンギュンの声は暖かく深みがあってセクシーで、人を安心させる不思議な力がある。絶望の淵にあるジアンが、「いい子だな」착하다というドンフンの声を何度も繰り返して再生して聴くシーンがあったけれど、彼女はあの声に救われたのだなと思う。最後の再会の場面も、姿よりも声がさきに聞こえてきて、あ、彼がいる、とわかるのだった。「おじさんの声、言葉、考え、足音、全部好きでした」
イ・ソンギュンは、以前見たコン・ヒョジンとの共演のパスタのドラマではそのパワハラを絵に描いたような強圧的な役柄にうんざりして途中離脱したけど、このドラマでは、なにか生きることに倦んだような、「真面目な無期懲役囚のような」影のある中年男をていねいに演じていた。
若い女の子と二人で食事というだけでそっち方面の妄想がふくらむ中年男の助平根性にはうんざりするが、そのような下心をまったくもたないドンフンの清廉さが素敵。下働きの派遣社員にも、わけへだてなく礼儀をつくす正しさも。
こんな中年男性もいるのね。
この人は本当の紳士だと思ったのは、清掃員のおじさんにていねいにおじぎをする場面。ジアンにひそかに助けの手を差し伸べていたことを知って「尊敬します」と頭を下げるところ。そういえば彼の兄弟も清掃をなりわいとしているのだった。職業に貴賤はなく、明日は自分もその仕事をするかもしれないのならば、その人に敬意を表すのは当然のはずなのに、そうする人は少ない。
建築設計エンジニアという仕事柄だろうか、いつもバランスを心がけるドンフンの、建築物の内力(内側から支える力)と外力(外からの風や荷重や振動など)の均衡の話から、それを人間にたとえて、人間を内側から支える力についての話が面白い。他人から軽蔑されたり攻撃されたりしても、しっかり自分を支えるだけの力があるかどうか、その力は何に由来するのか。
ダークスーツの男ばかりの会社の出世争いの世界の中で、派遣の分際で、とバカにされてもくじけるどころか、怯むことなく、かえって彼らを翻弄し狼狽させるジアンの力強さが印象的。履歴書の特技の欄に「かけっこ」とだけ書く、学歴も職歴もない、何ももたない彼女が、強欲な高利貸しに殴られても、憎悪の視線で強く見返すしたたかさをもつ。強靭な建築物が内なる力だけで外圧に持ちこたえるように。
特技がかけっこで、自分の足だけを頼りに走るジアンに対して、ドンフンには特技らしい特技もない。無駄に学歴ばかりあって、つぶしがきかなくて、息子に特技の動画を頼まれると困惑してしまうが、友人や兄弟の協力で何とか切り抜ける。たった一人で走るジアンと、周囲に助けられて生きるドンフンの違いが際立つ。
彼女の賢さがよくわかるのは自分を殴るようにドンフンに言う場面。ト社長にドンフンに求愛するように命令され、あとから証拠として録音を聞かせなければならない。しかし、ドンフンを陥れようとする一派に親密な写真を撮られてはならない。そこで、わざとドンフンを怒らせて殴るように仕向けるのだけれども、その憎まれ口の中にも、彼を心から愛して尊敬する気持ちを盛り込むのを忘れない。
ジアンの入り込んでしまった貧困層のヤングケアラーという袋小路の苦悩がつらすぎる。中卒で親にも見捨てられては、どのように生きていけばいいか途方に暮れるのも無理はない。相続放棄や無料の介護制度などの情報も、彼女たちには届かない。その袋小路から、ドンフンに助けられながら、少しずつ生きる力をつけてゆくジアンの成熟がまぶしい。
それにひきかえ、男とはつくづく弱い生き物だなと思う。どんなに強がっても、どんなに高学歴でも、地位が高くても、ひとたび弱みを突かれるとあっけなく崩れ落ちる。互いの弱みを握るために社内の至るところに監視カメラをつけて監視し合うというのも、クソみたいで気が滅入る。
ドンフンの兄と弟も、そういう弱い男の典型で、事業に失敗したり妻と別居したりするだけで落ちぶれて、詰んでしまう。その兄弟たちのサブストーリーも見ごたえがあって、酒を飲んでは母親に叱られる情けない中年男たちが、それでも仲間と励ましあいながら、小さなビジネスをはじめて、新しい道を摸索してゆく。必ずしもカップル成立のハッピーエンディングとならない結末も、嘘っぽくなくて良い。
人生も下り坂になって、今さら何を始めるのも遅すぎて、やり直しのきかない年齢とあきらめるよりも前に、幸せになろうという意志を強く持って、自らの可塑性を信じてみようよ、というメッセージがきこえてくるような気がする。
可塑性といえば、強欲一点張りのはずの借金取りが、終盤で見せる涙とともに、それまでの彼には似合わない思いがけない行動に出る結末も、彼のような人間にも変わる可能性があることを教えてくれる。
日本人にはピンとこないが(それともピンとこないのは私だけ?)、韓国人の男にとって、親の葬式を立派に執り行なうことが、人生の優先順位のかなり上位にあるようだ。沢山の人に参列してもらうこと、花輪や供物をどっさり飾って故人を送ることがこの上なく重要で、それは単なる見栄なのか、儒教的伝統の呪縛なのか、ずいぶんつまらないことにこだわっているようにも見えて、それでますます自分の首を絞めているようにも思えるのだけれども、それでも、最終話のお葬式はじんわり心にしみてくる。さみしかった祭壇に、いつの間にか供物が並べられ、花が飾られ、弔問客が次々に現れて、にぎやかな宴が始まる。
女の人が喪服を着るときに、頭の横のところにつける小さな白いリボンがかわいい。
いつか偶然に再会したときは笑顔で、と約束して別れた二人の、ラストシーンでの再会で、約束通りの、それまで一度も見せなかったような輝かしい二人の笑顔がほんとうに素敵。雪のちらつく長い長い冬のシーンがずっと続いていたが、このラストでは、明るく暖かい春の日差しにあふれていた。

このドラマについてはいくらでも語りたいのだけれど、あとひとつ。
15話、バレてしまったあとの病院での、ジアンとドンフンの会話で、ジアンが、私のことを恨んでいないのですかと尋ねたのに対して、ドンフンは「その人のことを知ってしまえば、その人から何をされても関係ない。そして僕は君を知っている」と言う。
しかし、ドンフンは、妻のユニの婚外恋愛を知った時は、取り乱して怒り狂ったのだった。彼は妻のことをよく知っていたはずなのに。
いや、知っているつもりでも、本当の意味で知っているとは言えなかったのかもしれない。結婚生活を続けるにつれて、いつのまにかすれ違いが多くなり、相手の問いかけに生返事で答えることも多くなるうちに、互いのことがだんだんわからなくなってゆく。
ドンフンがユニに語りかける言葉の中で「何か要るか?」という言葉がいちばん温かかった、とジアンは言う。相手を気遣う優しいことばのはずなのに、倦怠期の夫婦にとっては内容空疎な音でしかなくて、言われた方はその優しさに気づけないし、言う方も、いつもの惰性で言っているだけで、心がこもらない。ことばにこめられているはずの優しさに気づけるのは、皮肉なことに、ジアンという婚外の人間なのだった。
誰かを本当に知るというのはどういうことだろうか。旧約聖書では、「女を知る」と「女と性交する」は同義だったらしい。しかし、性交したり結婚したりしたからといって、その人のことをほんとうに知ったことには必ずしもならない。逆に、そのような関係でなくても、あるいはそのような関係ではないからこそ、その人のことを深く知ることもありうるのかもしれない。
それで思い出すのは、ジョンヒとジアンの関係性で、数日間ジアンを泊まらせてほしいとドンフンから頼まれたとき、ジョンヒが、そのわけを尋ねようともせず、喜んで迎え入れるところ。その人の境遇や経歴などを中途半端に知ってしまうと、知っていることがかえって邪魔になって、その人の深いところを知る妨げになりうる。何も知らないことこそが、その人を深く知る助けになる、と言えるだろうか。そして、ある人を深く知るとき、それはその人を愛することに限りなく近づく。
ある人について、どれだけ多く知っているかということと、どれだけ深く知っているかということは別のことなのだろう。たしかにジョンヒはジアンについて少ししか知らないけれども、深く知った。だからこそ、盆と正月を一緒に過ごす約束をした。
さきほどのドンフンのことばに戻るならば、その人のことを深く知ることによって、深い信頼が生れるとき、もはやその人からどんなことをされても、信頼がゆらぐことはない、ということを彼は言おうとしているかもしれなくて、そのような深い信頼を、誰かに抱いた、あるいは誰かから抱かれたことはあっただろうか、と、ふと自らに問いかけたくなる。