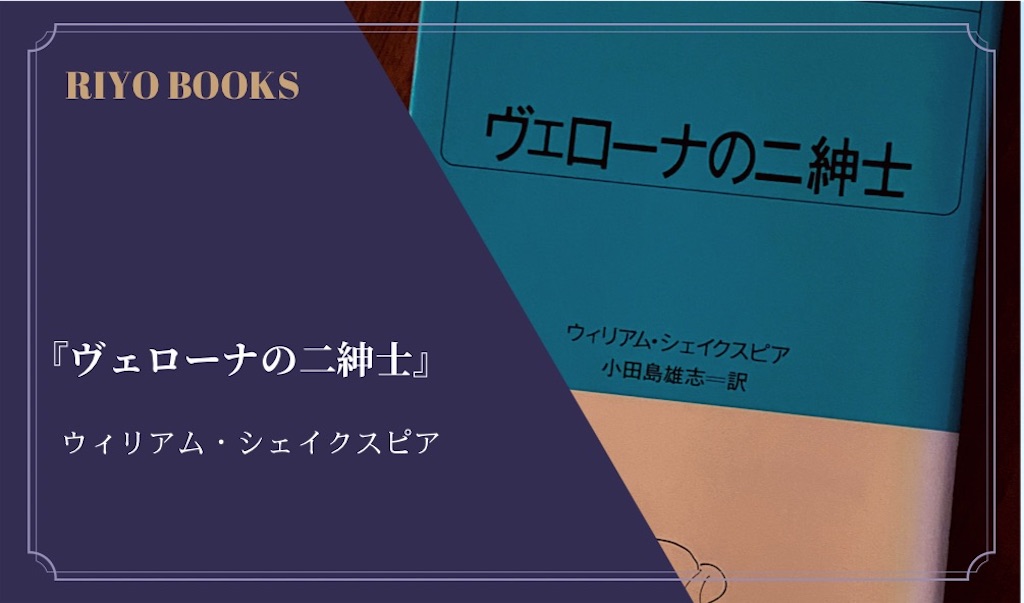こんにちは。RIYOです。
今回はこちらの作品です。

第二次世界大戦争を経て、それまで隆盛していた日本の文学は大きく変化しました。空襲によって与えられた凄惨な経験と、戦禍によって与えられた精神への強烈な苦痛は、文学という形を通して新たな思想や哲学となり、第一次戦後派という思潮を生み出しました。その後、復興に伴い流れ込んできた西欧の文化や芸術に感化され、戦争を生き抜いた人間が新たに構築した思想や哲学を打ち出す西欧型の長編小説を量産した第二次戦後派が生まれます。このように西欧化していく文芸思潮から、戦前文学の主流となっていた私小説への回帰を目指そうとする文芸思潮が現れました。これが「第三の新人」と呼ばれる作家たちです。安岡章太郎、吉行淳之介、庄野潤三らが代表として挙げられ、今回の遠藤周作(1923-1996)もその一人です。
遠藤周作は、カトリックとして生涯を苦悩しながら生きた作家です。銀行員の父親の転勤によって幼少期を満洲で過ごしましたが、両親の離別によって母と日本へ帰国します。伯母(母の姉)の家に身を寄せましたが、カトリックであった彼女の勧めによって教義を学び、洗礼を受けて入信します。灘中学への進学までは順調に進みましたが、その頃から読書や映画に耽溺して勉学が疎かになっていきました。高校受験は苦難の連続で、浪人生活を経てイエズス会の運営する上智大学予科へと進学しましたが、肌に合わずに退学してその後も受験を繰り返して失敗します。精神への負担が起因したのか、その頃から肺を病み始め、その闘病は死ぬまで続きます。受験の失敗が続いて母親に経済的負担をこれ以上与えられないとして、帰国していた父親に頭を下げて同居を願いました。この進言は旧制高校か大学の医学部予科へ入学することを条件に許可されましたが、受験は全て失敗に終わります。そして自分の力量と関心の強さに合わせた慶應義塾大学文学部予科へ、父親に学部を伏せたまま受験を報告して補欠合格しました。しかし真相が明るみになると父親は激怒して、遠藤を勘当してしまいます。生活する場を無くした彼は、友人の利光松男(後に日本航空の民営化に携わる)を頼って宿を借り、縋るようにカトリックの学生寮へと入ります。そして、その寮の舎監である吉満義彦の紹介によって出会った堀辰雄の影響で、熱心に勉学と読書に励み、心を入れ替えたように文学者への基盤を構築していきます。
その頃、激化していた第二次世界大戦争の戦局は悪化の一途を辿りましたが、遠藤は肋膜炎の罹患などを理由に兵役に就くことなく終戦を迎えました。戦後は大学に戻ってカトリック作家を中心にフランス文学へと傾倒していましたが、その勉学に励む姿勢を見た父親が、遠藤との関係を緩和させて再び家に招きました。環境の安定と熱心な勤勉によって生まれた初めての評論は神西清の目に留まり、文芸評論を中心に執筆を進めていきます。そして、寄稿していた『三田文学』にて正式に同人作家として歩み始めました。その後、更なるフランス文学の研究として、国内初のフランス留学生として欧州へと渡ります。渡仏中には肺の病が悪化して病院を渡り歩くことになりましたが、それでもルポルタージュを中心に筆を進めて、エッセイや小説などを執筆していました。国内に戻ると作家として本格的に活動を開始し、1955年に『白い人』で芥川賞を受賞します。肺の病が度々悪化して生死を彷徨う経験をしながらも、『海と毒薬』(1957年)、『わたしが・棄てた・女』(1964年)、『沈黙』(1966年)、『イエスの生涯』(1973年)、『侍』(1980年)など、多くの作品を生み出していきました。
遠藤はフランス留学で経験した「日本人でありながらキリスト教徒であるというある種の矛盾」を、生涯にわたって抱えながら生きていました。幼い頃に受けた洗礼は、日本という国の環境で育ち、日本の信仰(主に仏教)の風習を体感して育てられた彼の心に、絶対的なイエスの信仰やローマ教皇の権限に賛同できないながらも賛同しなければならないという苦悩の枷を与えます。背信的な感情は微塵もなくとも、カトリックの唱える、神の存在や信仰の在り方に疑問を抱き続けます。そして、彼が長年この悩みに時間を費やして導き出した持論と、生涯晩年に迫る「死」の存在を意識した「神と転生」という主題を、一つに集成して生み出した作品が本作『深い河』です。
磯辺、木口、美津子、沼田、大津、それぞれの登場人物たちは人生で与えられた苦悩を抱いて、母なる大河「ガンジス川」に導かれます。「愛とは何か」という問いに答えを求めるように、自身の人生を振り返り、過去の出来事に苦しみながら、それでも「愛」を求めて日本からインドへと辿り着きました。遠藤が自身の思考と結びつけたのは、グレアム・グリーンの作品から影響を受けた「人間の哀しさ」でした。
人間の哀しさが滲む小説を書きたい。それでなければ祈りは出てこない。
グリーンの『燃えつきた人間』を読み始める。いかにも壮年、五十代の小説という作品だ。五十代は迷いの多い年齢という意味でだ。ここにはグリーンの人生の、信仰の迷いが叩きこまれている。私の今度の小説だって同じだ。違うのは七十歳近くになっても私の人生や信仰の迷いは、古い垢のようにとれない。その垢で私は小説を書いているようなものだ。
遠藤周作『深い河 創作日記』
第一の登場人物「磯辺」は、信仰を持たない戦後の典型的な日本人男性として描かれており、宗教を持たずに仕事に精を出し、それが家庭への還元であると考える人間でした。しかし、妻の死によって与えられた空虚さはどこから来るのか、生活だけを追っていた自分は人生を失っていたのではないか、といった自問に捉われます。妻が最後に残した「転生」の強い意志に、今まで妻を顧みなかった懺悔の思いを重ね合わせて、できる限りの行動を起こして「妻の転生」の可能性を追ってインドへとやってきます。この「妻の死」から生死を見つめ直し、生活の挫折と人生の再発見に気付き、自身の生を考え始めます。
木口という人物は、第二次世界大戦争時に同時的に発生していた英国領インド及びビルマが独立を目指した戦争において、日本軍が介入して英国軍や米国軍と激しい衝突を繰り広げた「ビルマの戦い」での生還兵でした。襲いくる連合軍から身を守り、届かない配給を頼りに身を隠し、味方が目の前で飢えながら倒れていく姿を見てきた木口は、塚田という同僚と地獄絵図のなかを彷徨い歩きました。ここに示される「死と救済」や「恐怖と咎」は、当時の復員兵が精神に強い傷として負ったものが描かれ、戦後の日本を生きる困難さが垣間見えます。そこには、肉体と精神の「死」の問題が大きく映り、木口は同胞たちの魂を救済すべく、母なる河を求めてインドへとやってきます。
童話作家の沼田は、遠藤が幼少期を過ごした満洲での背景を背負っています。原住民との出会いと別離、愛犬との出会いと別離が、彼の心の奥底に「後悔的な記憶」として残されます。そして肺を患う点も遠藤と重なり、生死を懸けた手術を行います。身代わりのように亡くなった九官鳥に、神の如き力を感じ、その恩返しをするために母なる河へと向かい、救ってくれた九官鳥(に見立てた別の九官鳥)を救済します。ここには、動物をイエスの象徴として描こうとする遠藤の意図が含まれており、「生死と魂」が沼田と動物の会話を通して神性を表しています。
神は人間の口を通して語りかけると言うが、時として神は鳥や犬や人間がペットとして愛する生きものの口を通しても語りかけるのではないだろうか。
遠藤周作『深い河 創作日記』
それぞれの『魂の問題』を苦悩として抱きながらインドへのツアーに参加して物語は進みます。母なる河へと向かう彼らは、「人間は死後に希望を得られるのか」という「心の救済」を求めています。それは「愛」とも言い換えることができ、特定の信仰のない日本人にとっての救いという問題が本作で主軸となって描かれ、カトリック作家としての遠藤が、主題として苦悩のうえでの一つの答えを示しました。
遠藤は、イギリスの哲学者ジョン・ヒックの宗教多元論に影響を受けています。これは、文化の相違や宗教の相違によって構築された社会的価値観を尊重して、良心に応じて様々な宗教を選択することができるという権利や自由、そして安全を与えられるべきであるという考えです。排他主義的な宗教における「神の在り方の矛盾」に悩まされる人々は、この考えに賛同して支持し、遠藤もまた自身の抱える「神に望む在り方」に理解を示す考えとして作品を通して同調しています。晩年となった彼は、死に向かう焦燥によって魂や転生といったことへ意識が強く向かい、「一日一日、自分の人生が終りに近づきつつあることを感じない日はない」と日記にあるように、差し迫る「死」についての恐怖を抱いていたことで、「神の救いによる死」を望んでいたことが窺えます。
生も死も、善も悪も、すべてを包み込んで流れていく偉大なガンジス川は、インドで雄大に流れています。ヒンドゥー教徒のみではなく、どのような信仰を持っているものでも拒絶することなく、それぞれの人生を清濁合わせ飲むように魂を流してくれる存在です。ヒンドゥー教における河の女神ガンガーの名を持ち、ガンジス川はその化身として人々の魂を浄化すると考えられています。その水には聖なる力があるとされ、河での沐浴によって現世の罪を洗い流して、女神による浄化を受けると考えられています。また、この沐浴によって冥界で苦しむ先祖の霊魂を幸福にし、先祖の魂を浄化させて輪廻転生を促すとも言われています。本作後半の舞台となるヴァーラーナスィは、ヒンドゥー教、ジャイナ教、仏教の聖地で、インドの文化的中心地でもあります。ここは、瀕死の状態でガンジス川を目指す人々が望む「救済的な死」を手助けする土地でもあり、死の儀式が頻繁に行われる「死者の都」として知られています。インドの人々はガンジス川に流されることを魂の望みとして抱いています。それは彼らが「ヴァルナ」と呼ばれるカースト規制の考え方を持ち、善行による魂の浄化によって来世を幸福なものとすると信じ、飢餓や病苦に苦しめられても最期にガンジス川に流されれば魂は報われるという強い意識を持っているからであると言えます。このような価値観と目の前に繰り広げられる沐浴と死の儀式に、インドを訪れた登場人物たちは、人生の意義と魂の救済を目の当たりにするように衝撃を受けます。
主題の中心となる大津と美津子は、「人間愛」についての探究が描かれています。「誰かのため」ではなく、「愛のため」に生きている大津の言動を、「自分のために」生きる美津子には理解ができません。ピエロと表現される大津とガストンという介護ボランティアは、場面こそ違いますが同質の存在として描かれています。無力でありながらも懸命に他者の苦悩を受け止めようと「愛」を持って接します。
わたしは神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。わたしは、キリストと共に十字架につけられています。生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。わたしが今、肉において生きているのは、わたしを愛し、わたしのために身を獻げられた神の子に対する信仰によるものです。
『新約聖書』ガラテヤの信徒への手紙 第二章第十九-二十節
大津とガストンの行動はイエスに倣っていると言えます。愚かで醜く、愚鈍と思われながらも、人々の苦しみや悲しみを包み込むように受け止めて、少しでも助力しようとする「無償の愛」が、イエスの在り方と重なって彼らの言動から感じられます。
ここで遠藤周作は「担架に乗せられた時、大津は羊のような苦痛の声をあげた」と書いている。私たちはもう「羊」がキリストを表すことを知っている。美津子が何の気なしに拾い読みした「イザヤ書」のすぐ先に、次のように書かれているのだ。
「彼はみずから懲らしめをうけて、
われわれに平安を与え、
その打たれた傷によって、
われわれはいやされたのだ。
われわれはみな羊のように迷って、
おのおの自分の道に向かって行った。
主はわれわれすべての者の不義を、
彼の上におかれた。
彼はしえたげられ、苦しめられたけれども、
口を開かなかった。
ほふり場にひかれて行く小羊のように、
また毛を切る者の前に黙っている羊のように、
口を開かなかった。
彼は暴虐なさばきによって取り去られた。
その代の人のうち、だれが思ったであろうか、
彼はわが民のとがのために打たれて、
生けるものの地から断たれたのだと。」
(「イザヤ書」第五三章五-八節、一九五五年改訳による)旧約聖書において、イエス・キリストの出現を予め告げているとされるこの個所が『深い河』の大津の生き方(あるいは死に方)の基調低音をなしている、と言って良いだろう。そして「無力なイエス」という主題は遠藤周作の到達した地点であった。
井桁貞義『ドストエフスキイ 言葉の生命』
フョードル・ドストエフスキーの『白痴』におけるムイシュキン公爵を、大津の言動と重ね合わせて読み解く井桁貞義はこのように述べています。ラゴージンの精神が乱れ、奇異な言動を繰り返す生命の最期を見守る場面では、ムイシュキンは何ひとつ彼のためにできることがありませんでした。ただ涙を流して寄り添い、無力な同伴者として傍に佇むのみでした。
奇跡を起こす神的存在のイエスではなく、無力でありながら包み込むような存在のイエスこそ、復活(転生)の意味があり、同伴者としての心的支柱という信仰の根源的な存在足り得るものだと遠藤は考えます。大津、或いはムイシュキンの言動からは白痴的な印象を確かに受けますが、そこには絶対的で無力な同伴者としての人間愛が存在しており、それはイエスの言動とも繋がっているものと考えられ、彼らの言動はただの神の真似事ではなく「真の信仰における深い愛」が込められているということが理解できます。
だが我々は知っている。このイエスの何もできないこと、無能力であるという点に本当のキリスト教の秘儀が匿されていることを。そしてやがて触れねばならぬ「復活」の意味もこの「何もできぬこと」「無力であること」をぬきにしては考えられぬことを。そしてキリスト者になるということはこの地上で「無力であること」に自分を賭けることから始まるのであるということを。
イエスはその愛を言葉だけでなく、その死によって弟子たちに見せた。「愛」を自分の十字架での臨終の祈りで証明した。
遠藤周作で読むイエスと十二人の弟子
イエスを体現する大津がカトリックに拒絶され、辿り着いたのがヒンドゥーの女神ガンガーでした。無力ながらも愛を持って、ガンジス川まで辿り着くことができない人々を「魂を救済」するために寄り添って連れて行きます。その存在は、多くの人々に理解されませんが、助けられた人々は神を見たように感じるのだと思います。大津は不憫な最期を遂げますが、その姿を見て心に影響を受けた美津子は、やはり「無力なイエス」を彼に見たと考えられます。妻を失った磯辺同様に、亡くしたものは心に生きています。これこそが「復活」であり「転生」であるという解釈も可能だと言えます。神性を受け継ぐように魂を胸に抱き、思い返すたびに転生を感じる、このような考えも一つの信仰であると感じました。
遠藤周作の晩年に発表された本作『深い河』。未読の方はぜひ、読んでみてください。
では。